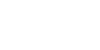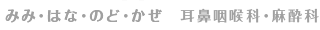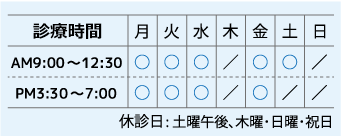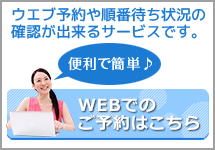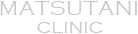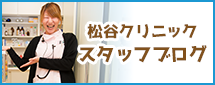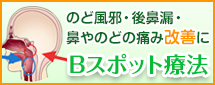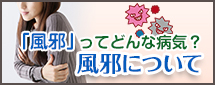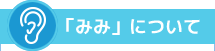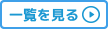かぜをひいたときに耳がつまったように感じるのはどうしてですか?
2014年09月26日 18:38 カテゴリ: 「みみ」に関する質問
かぜをひいたりすると外気圧と中耳内の気圧のバランスをとるために重要な働きをするの耳管の開口部にある「鼻咽腔」というところに炎症が広がります。
粘膜のはれや分泌物の増加などにより耳管の働きが悪くなり、つばを飲み込んだりあくびをしても中耳に空気を送り込むことができなくなり、違和感を感じます。
これを「耳管機能不全(耳管狭窄症)」といいますが、この状態になると中耳の粘膜やはれ、浸出液のしみ出しがみられるようになり、いわゆる「滲出性中耳炎」を起こすことになります。
子供が鼻をよくすすります。なぜでしょう?
2014年09月26日 18:38 カテゴリ: 「はな」に関する質問
鼻すすりの原因は鼻の中に溜まった鼻汁を除去するための動作です。
すすられた鼻汁は上咽頭に停滞し無意識に飲み込まれます。
しかし鼻すすりの癖は鼓膜をへこませ各種の耳の病気を引き起こす原因となります。
特に中耳疾患としてよく知られる「滲出性中耳炎」を長引かせたり、治りにくくなる原因となります。
適切な鼻の治療を受け正しく鼻をかむ習慣をつけましょう。
また疾患がないのに鼻をすする「心理的要因による鼻すすり」もあるため、時には心理的背景がないかよく注意、観察してあげてください。
鼻が詰まるので市販の点鼻薬を買って使用しています。
2014年09月26日 18:37 カテゴリ: 「はな」に関する質問
市販の点鼻薬は「血管収縮薬」といわれ、即効性にくわえ爽快感と満足感をもたらしますが、あまりに有効なために鼻腔の機能が正常ではない状態におかれてしまい、長時間続けると効果の持続時間を短縮させ鼻づまりが進行して頻回に投与を繰り返す悪循環に陥ります。
すると鼻の粘膜に障害が起こり効果的な治療が難しい「点鼻薬性鼻炎」を引き起こします。
市販の点鼻薬の突然な使用停止は著しい鼻閉塞を引き起こしますので医師と相談の上計画的に使用を止める適切な治療を受けましょう。
痰が多く、咳も出ます。鼻が悪いことと関係がありますか?
2014年09月26日 18:37 カテゴリ: 「のど」に関する質問
副鼻腔炎と気管支の炎症やぜんそくが合併することがあります。
鼻汁や鼻づまりがあると、口呼吸のために加湿・加温・清浄化されない空気が吸入されたり鼻汁がのどのほうにおり、気管支に入って気管支炎やぜんそくの症状をひどくさせることがあります。
特に子供の場合、鼻汁がのどにまわってくること(後鼻漏)が刺激となって咳やたんが続く事がありますので注意しましょう。
このような場合は副鼻腔炎の治療をすることで咳やたんの症状が良くなることがあります。
風邪の時にどうしてお風呂にはいってはいけないのでしょうか?
2014年09月26日 18:36 カテゴリ: その他の質問
子どもが風邪にかかった時、入浴させるかどうかはご家族にとって身近な問題と言えます。
特にダメという理由はありませんが、子どもが高熱を出している場合や、明らかにぐったりとして体力を消耗している場合は入浴は厳禁です。
解熱し、回復に向かいつつある場合は「長時間入浴しない」「頭を洗ったらよくドライヤーで乾かす」「湯冷めさせない」「入浴後すぐに寝かせる」などの約束を守ればお風呂に入ってもいいでしょう。
子どもを耳鼻科に連れて行くと泣いたり暴れたりして診察してもらえません。
2014年09月26日 18:35 カテゴリ: その他の質問
耳鼻科に行くとなると子どもは「何かされる」、「こわい」と感じて拒否の態度に出てしまうことがよくあります。
『治療が必要』だということを保護者の方からもお話ししてください。
なるべくお子さんには負担のないよう、また痛くないように治療にも気を付けていますが、どうしてもある程度の我慢が必要な時もありますので、保護者の方も「動かないでいようね」、「じっとしてたらすぐ終わるからね」と励ましてあげてください。
こちらに、当院のお子様の治療に対する思いを掲載しています。
https://www.matsutani-ent.com/blog/children
耳鼻咽喉科の通院はなぜ長くなるのでしょう?
2014年09月26日 18:35 カテゴリ: その他の質問
耳鼻科領域の病気は慢性的なものが多いです。たとえばアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎があります。アレルギー性鼻炎の場合、環境を変えると発症しなくなることもあるでしょう。
子ども成長発達が著しいので、アレルギー反応も活発になって、症状がはっきりと表れてしまうことが多いです。
ほかにも副鼻腔炎、中耳炎(中でも滲出性中耳炎)などがありますが、子どもは大人と違ってみみやはなの機能が未熟なので通院が長くなるのはやむを得ません。
なるべく症状を軽くおさえ、お子さんにあった治療方法をみつけて自分である程度のコントロールができるようになるまで焦らず気長に治療を続けましょう。
抗生物質は長く続けて服用してもいいのでしょうか
2014年09月26日 18:34 カテゴリ: その他の質問
抗生物質は細菌の発育や繁殖を抑えたり殺菌の効果がある薬です。服用期間は病気によって異なり、対象となる細菌をやっつけるのに必要な期間で処方していますので、自己判断で服用を止めたりせずきちんと飲み続けてください。
抗生物質を長期間にわたって服用する事により、その細菌に対する耐性ができてしまい、次に同じ薬を使っても効かなくなるという『耐性菌』にならないよう、いろいろな種類の抗生物質を必要最低限度で投薬しています。
その他、慢性炎症を改善させる作用もあり少量ずつ長期間使用する治療法もあります。
この療法は抗菌力に依存しない作用ですから長期間の服用により細菌が耐性化し、効果が減少するという心配もありません。
ただ、このような目的で服用する場合は長期間しっかりと飲み続けることが大切です。
子どもが1日3回食後の内服薬をもらったのですが、学校(幼稚園、保育園、小学校など)ではどうしたらいいでしょうか?
2014年09月26日 18:34 カテゴリ: その他の質問
多くの薬は決められた飲み方をきちんと守ることにより、初めての効果的な働きをしますが、服用時間が多少ずれてもあまり問題がない薬もあります。
適当な間隔で1日3回飲ませれば大丈夫という薬でしたら『朝食後⇒帰宅時⇒寝る前』の3回を目安に飲ませてください。
学校に薬を持参し、自分で飲めるお子さんには飲めたかどうかの確認の声かけを学校の先生等にお願いしてください。
子どもがどこも悪くないのによく咳払いをするのですがなぜでしょう?
2014年09月26日 18:31 カテゴリ: 「のど」に関する質問
咳払いは「わざと咳をする行為」の、喉に軽い炎症や魚の骨などが引っかかっていたり、扁桃肥大や鼻炎など気導内の異物や刺激を取り除く為に行う場合と、情動行動(比較的短期の感情の動き。主に「興奮」が中心的であるが、「不安」「快不快」も情動として扱えるとされる。(ウィキペディアより))、癖と考えられる場合があります。
症状自体は軽くても持続する咳払いの原因となります。
初期の気管支炎や肺炎、気管支ぜんそくなどが原因にあげられ、重症になれば呼吸困難や発熱の症状がみられるため、小児科の受診を考えてもいいでしょう。
異常が認められない場合、心因性やチック障害などを疑うことがありますので、精神科医や児童心理カウンセラー等に相談する事があります。